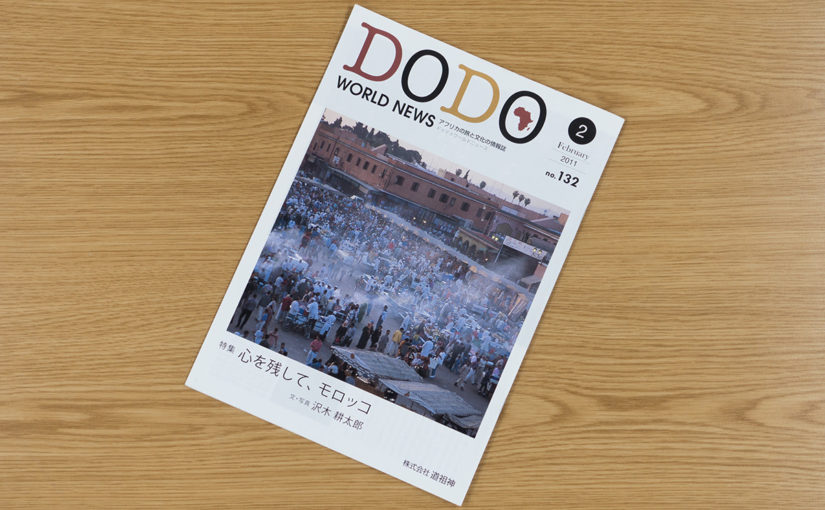ホワイト・シティーからソウェタン憩いの場所、トコザ・パークへ
ジャバブ地区にある蒲鉾型の家は3軒長屋ですが、その壁が白いことから、その家がある辺りは通称ホワイト・シティーと呼ばれています。ホワイト・シティーは不良が多いので危ない、あの地区は他のソウェトとは違うから気をつけろと言われていましたが、私は不良ですと言う看板をぶら下げている人がいる訳でもなく、他の地区と雰囲気が違う訳でもなく、家の形がちょっと変わっているな~という程度の違いです。

そのホワイト・シティーを抜けると、トコザ・パークに出ます。トコザ・パークは道路によって幾つかに分れており、クリケット場があるエルカスタジアムは、ワールドカップの時のファンパークになりました。トコザ・パークというと、オールド・ポッチェフストローム沿いのモロカ警察署の並びで、緑が多く、池と小川があり、週末にはブライ(南アフリカのバーベキュー)をする人達がいたり、結婚式の記念撮影に来たり、時々コンサートがあったりする、ソウェタンの憩いの場所です。ワールドカップ時にはその公園にも大型のテレビが置かれ、FIFAのファンパークとは別にタウンシップテレビというワールドカップ無料観戦場になっていましたので、ネルソン・マンデラ元大統領の写真があるその公園の写真を新聞などで見た人がいるかも知れませんね。ちなみに私は、あるテレビ局の仕事で極寒の中にバファナバファナ対ウルグアイの試合を、そこのテレビで観戦しました。
ソウェトで最も有名な場所の一つレジナ・ムンディ教会

トコザ・パークの隣には、ソウェトで最大のカソリック教会、レジナ・ムンディ教会が建っています。レジナ・ムンディとは、ラテン語で世界の女神という意味だとか。この教会は6,000人がミサに出席できるという大きな教会で、ポーランド大統領夫人から寄付されたステンドグラスがあり、ブラック・マドンナの絵(アパルトヘイト時代に、オッペンハイマー家の当主ハリー・オッペンハイマーの依頼で画家が描いた、黒人のマリアとキリストの絵で、下の方の絵はソウェトを表している)が有名です。
アパルトヘイト時には、ソウェト蜂起の犠牲者の葬式など何回も合同葬儀が行われ、反アパルトヘイト活動家がミサを利用して集会をやったりしていましたので、反アパルトヘイト集会を阻止する為に、警察の襲撃を受けた事もあります。この教会内では虐殺は行われませんでしたが、警官隊が解散を要求した時に、銃座でたたき割られたテーブルや、天井の数か所に残された、威嚇射撃の弾の後を見る事ができます。
この教会でのデスモンド・ツツ大司教のお祈りや、反アパルトヘイト運動のリーダー、ドクター・モタナの演説などの映像、ソウェト蜂起時に学生たちが逃げ込んだ時の写真、ソウェト蜂起追悼記念式典を反アパルトヘイト集会になるという事で警察が襲撃した時の映像・写真は、アパルトヘイト博物館やヘクター・ピーターソン博物館などで見る事もでき、ソウェトで最も有名な場所のひとつです。教会の2階には、1950年代~ソウェト蜂起の時代~アパルトヘイト後の写真のエキジビションがあり、それも見所の一つです。
元々キリスト教会は誰でも受け入れる所で、カソリック信者ではない単なる観光客、異教徒であっても入る事ができます(但し、ミサや何かイベントをやっている時には関係者以外は入れません)。教会なので入場料は無料ですが、かつては見学後、神父さんがいる建物の献金箱に献金を入れていました。教会の人が案内してくれた時には、その献金の事も教えてくれますが、案内者が誰もいない時や他の人の相手をしている時でも自主的に献金していたのですが、ワールドカップの影響で観光客が増えたせいか、最近では教会内に入った所に係の人がいて、博物館で入場料を取られるように献金をお願いされ、世知辛くなったとも言えます。しかし、ツアーガイドとしてはお客さんを連れて行きやすくもなるので、有難いとも言えます。
ソウェト(Soweto) 南アフリカ共和国ハウテン州ヨハネスブルグ市にある地域。地名の由来は“South Western Townships”(南西居住地区の短縮形)。アパルトヘイト政策によって迫害されたアフリカ系住民の居住区として知られる。観光では、ソウェト蜂起の際に警官に射殺されたヘクター・ピーターソンや反アパルトヘイト運動を率いたネルソン・マンデラの記念館が有名。